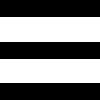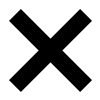写真が好きだった
民族の歴史文化を歌や語りで口頭伝承として残してきた中国・貴州省の苗族(ミャオズー)。写真家・田中一夫氏は、この20年、苗族の生活を撮り続けてきた。かつてコマーシャルやレコードジャケット等の撮影で活躍し、藤圭子(演歌歌手・宇多田ヒカルの母)のレコードジャケットの撮影でプロデビューした田中氏であった。
「親父が趣味でカメラ持っていた。ロードという素晴らしいマニュアルのカメラがあった。幼稚園の頃、そのカメラを革のケースに入ったまま紐をずるずると引っぱって歩いていたら、親父が真っ青になって飛んできた。それで、フジペットという簡単に写せるカメラを買ってくれた。その時から写真との付き合いが始まっていたのですね」と幼い頃を振り返る。
「自動車が大好きでカーデザイナーになるか町工場の車の修理工になりたいって、親父に良く言っていました。写真家になるなんて考えても見なかった」
中学の修学旅行で写真を撮りたくて母親に無理を言って「ペンタV2」という一眼レフを買ってもらったという。「写真が好きだったんです」
写真専門学校では商業写真を専攻。「すでに人を撮ることに強い意志をもっていた」
1970年代は学生運動真っ只中、同世代のエネルギーを撮りまくった。「大学紛争の時代を生きていました。いつも全学連の学生や機動隊の両方から追っかけられていました」
やがてレコードジャケットの写真家、須田豊氏のもとで二年間修行し、藤圭子のレコードジャケットやフランク永井のLP盤ジャケットを撮影した。
「アシスタントをしていて初めて仕事を任されたときは嬉しかった。『ありがとうございます』って平気で引き受けていましたが、今考えるとこわいですね。若さでやれたんですね」と、若い時代のエピソードは尽きない。
「先生は僕がやりたい様にやらせてくれた。世の中に知られている人の写真を撮らせてもらうことで自分に自信がでてきました」

苗族の村人と田中氏

苗族の家族と田中氏
何かを残したい
バブル時代の華やかで多忙な日々を夢中で走り続けていた。38歳。商業カメラマンとして多忙を極めていた。移り変わりの激しい消費文化の波のなかで「何かが違う」と心の奥で虚しさを少し感じていた。そして「世の中に残せる仕事がしたいと思うようになっていきました」
そんなある日、明治時代の人類学者・鳥居龍蔵先生の『西南中国調査報告』を目にし、興味を持ち他の学者の文献も見てみた。
「こういう民族がいるのかと、感動しました。歌の文化がある民族です。山や川で歌い合って恋を語るんですね、実際に『歌垣』をこの耳で聴いてみたいと思ったのです。これを機に、民族の写真をやっていこうという想いが募っていきました。その心に背中を押され88年に会社を辞めました」
苗族のことを本格的に勉強開始。「結婚三年目でした。世間から見れば無鉄砲ですよね。僕の行動を理解してくれたのは妻だけでした。おとうさんが思うようにやればいい……と」妻の作ってくれたおにぎりを持って毎日図書館に通った。
「草原のシルクロードの写真家、並河萬里先生に教えを請いたいとの思いで、再三通っていましたがいつも玄関払いでした」。やっと並河氏の奥さんの計らいで電話をいただいたが、「ドキュメンタリーの仕事はコマーシャルカメラマンにできっこない、身体壊すのが落ちだ」と、氏の言葉であった。
しかし、その一本の電話が「民族写真家として独立する原点の一つになったんです。勉強していく中で見えてきた。苗族の生活や文化を残していきたいと、勝手な使命感ですが」
苗族とともに
苗族の写真は「祭」を中心とした写真が多い「僕は彼らの普段の生活を撮りたいと思った」。図書館で苗族を調べていくうちに民俗学者の白鳥芳郎氏の名前が出てきた。
白鳥氏の研究室を訪ねた。学者の歩いてきた道を汚したくないからとの想いで先生にお会いした。38歳でこの道に入るのは遅くはありませんかと聞きました。先生は、僕が民族学をはじめたのは40歳からだよ、何か困ったことがあれば私の友人を訪ねなさい」と激励の言葉をいただく。
図書館で一年近く勉強し、89年7月、苗族の村を訪ねた。しかし、中国は歴史的過渡期にさしかかっていた。
「6月4日に天安門事件が起きるなんて思いもよらなかった。中国に着くと厳戒態勢で、県境ではカメラ機材すべてチェックされました」しかし苗族の村は中国の中央政治とは関係なかった。「何もなかったかのように僕をむかえ入れてくれた」
最初は車と通訳を頼んで中国取材を開始、しかし、自分の思うような自然体の苗族の写真は撮れず一人で村に入って行くことを決意。標高700メートルから1500メートルの山また山の中にある苗族の村々を訪ね歩いた。
「山で夏祭りがあり、念願だった『歌垣』を聴くことができた。男はなぜか高い裏声で歌い。娘たちはすごい声量で歌う、夜中じゅう、歌い合う『飛歌』はこちらの丘から向こうの丘に向かって歌い合うんです。それは素晴らしい歌声です」
苗族は、歌とともに生きてきた。恋を語るだけの歌だけではなく、子どもが生まれる時、客をもてなす時、人生の最後を迎える時も村人みんなで歌って送り出してあげる。歌とともに生きる苗族の生活には民族の歴史と誇りがあった。
「何気ないふだんの生活の中にこそ苗族文化はいきづいている、生活そのものが民族のアイデンティティーなのです」
日本と中国を何度も行き来し、苗族とともに歩んだ20数年。2011年10月、その集大成である写真集『歌とともに生きる 中国貴州省 苗族の村』(岩波書店)が発刊された。
―季節を変えては、同じ村に行き、同じ家族に会い、また泊まらせてもらう。前の取材で撮影した家族の写真を渡す。それを繰り返すことで、ゆっくりと苗族の生活に近づいていった―(『歌とともに生きる』「はじめに」より)

この写真は1990年1月に撮影。このときすでに女性たちの櫛は、プラスチック製の色鮮やかなものになっていた

香炉山の歌垣は、山頂で蘆笙を吹き鳴らす男たちの後ろについて、娘たちは反時計回りに踊っていく。雷山県の娘たちは、夏でもおしゃれな色のゲートルを巻いている

雷山県、朗徳上寨の歌垣

施洞の姉妹飯の祭りへ向かう村の娘たち

早朝の稲刈り。苗族はよく働く

王老吴一家の晩餐
失われゆく民族文化の記録
しかし、この20年、苗族の生活も急速に変化してきた。苗族の村でも携帯電話、インターネットが使われるようになり、若者たちの服装や髪型にも変化が大きく現れてきている。
「苗族だけ民族衣装を着続けなければいけない訳じゃない。時と共に生活文化は変化していく。しかし、今なお、苗族は誇りを持って生きている。彼らの心は僕の宝でもあります。燐としていて、ひとに優しい民族。20年もの間、僕は自分の原点の故郷を追いかけてきたのかもしれません。彼らの変化を見届けていくのも僕の仕事かな」
心の原点として好きな写真があると田中氏は言う。「バーシャ村の王老吴さんの家族が食事をしている写真です。僕は思う、普通の生活ができればそれで良いのだ、笑顔でご飯が食べられれば、それで良いのだ」と。
「苗族出身の民族学者、雷 秀武 先生のことばの中に『どんなに迫害を受け、弾圧され続けても怯まなかった苗族は不撓不屈の兵士であったと言えまいか』とある。かつて精魂込めて耕した田畑や故郷を捨てざるを得なかったが、『精神の故郷』を捨てることは決して無かった。
彼らはずっと兄弟のように自然と共生し・楽観的に苦難と向き合い、冷静に伝統を受け継ぎ、寛容な態度で変遷に直面するという生き方は『永遠に放棄と言わず』の精神を持って、苗族独特の『歌垣』で自分たちの歴史を口頭伝承として受け継いできた。歴史の中で苦労を重ねてきた人々だからこそ、人に優しくできる。人に優しい人は心の強い人なのだ。これが僕の苗族に対する長年の想いであり、この写真集は私の意図とは別に、失われゆく民族文化の記録となってしまったようです」
ドキュメンタリー写真家・田中一夫氏のことばは、レンズを通して見続けてきた苗族の村人への愛情にあふれていた。

肩に食い込む籾の重さは、収穫の喜び

稲刈りのひととき。カマキリを頭巾の紐に止め、「髪飾りきれいでしょ?」とおどけてみせる張格在さんの義理の妹

母さんはみんなが寝てからも暗い電灯の下、遅くまで機を織っていた

末っ子の留保生が鼻水まじりのおにぎりにパクついている。塩味がきいておいしそう

春節の日の朝、愛ちゃんのお母さんは「きれいに写してね」と言ったけれど髪飾りがうまく付けられないでいる

桃江村の髷の形はすぐに分かる

一家の柱は泰然自若。自信にあふれている

写真集『歌とともに生きる―中国・貴州省苗族の村―』