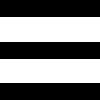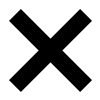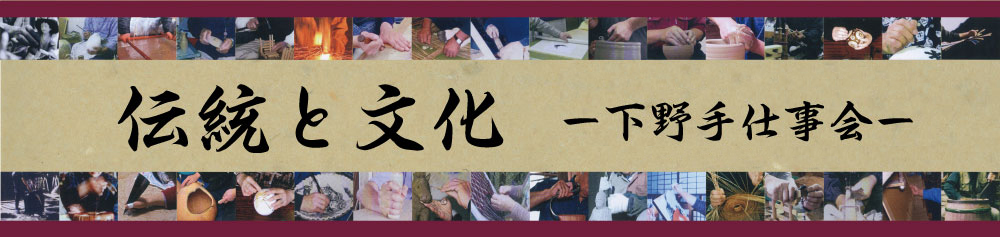
下野手仕事会の結成は尾島利雄氏(当時、栃木県立郷土資料館館長)、故大畑力三氏(武者絵)、故福田長太郎氏(烏山和紙)、渡辺浅市氏(間々田ひも)の各氏が発起人となり、栃木県内の伝統的手仕事の保全と伝承のため、県内各地の手仕事士を結合し、昭和49年栃木県立郷土資料館で設立総会を開き、産声をあげました。
記事一覧
-
No.40
下野手仕事会 展示即売会開催 「下野しぼり」の伝承者、諏訪ちひろさんに聞く
下野手仕事会の展示即売会が、このほど、栃木県立博物館1階エントランスで開催...
-
No.39
下野手仕事会、さくら市の建築遺産「瀧澤家住宅・鐵竹堂」で、初の長期開催
下野仕事会の展示会がさくら市の栃木県指定文化財「瀧澤家住宅・鐵竹堂」で開催...
-
No.38
下野手仕事会、サクラ満開の日光田母沢御用邸で、展示即売会開催
下野手仕事会(藤田眞一会長)の今年初のイベントとなる展示即売会が、4月...
-
No.37
下野手仕事会、恒例「手仕事展」 実演、体験でにぎわう 栃木県立博物館
栃木県内の伝統工芸品の職人たちの集まり、下野手仕事会による「下野手仕事展」...
-
No.36
石川錦城 -絹本画-
石川錦城(いしかわ きんじょう)さんは、絹本画を中心に活躍している作家である。1978...
-
No.35
樋口喜巳 -線香-
樋口喜巳(ひぐち よしみ)さんは、今から50年ほど前の1973年、線香製造の老舗「株式会社一心堂」で線香づくり...
-
No.34
須藤伸子 -結城紬織り-
結城紬の織り手として平成24年に栃木県伝統工芸士認定された須藤伸子(すとう のぶこ)さん。現在、30以上...
-
No.33
黒崎啓弘 -指物-
黒崎啓弘(くろさき けいひろ)さんは指物(さしもの)の技術・技法をもとに木工品を製作している「クロサキ工芸」...
-
No.32
若菜 萌 -筒描藍染-
筒描藍染とは、もち粉とぬかを蒸して作った防染糊を渋筒に入れて手で絞り出しながら模様を布に描いて藍染する技...
-
No.31
吉田 宏 -衣裳着雛-
仕事の上では、自分の手法の中で一貫する作業を施す、いわば一手で作り上げる十五人飾りを、世に送り出す雛づく...
-
No.30
山本 政史 -日光下駄-
私が県の伝統工芸展で、日光下駄の実演をするようになった頃に、手仕事会に入会の誘いがありましたが、当時は技...
-
No.29
柳 誠 -人形工芸-
父梅吉は大正11年栃木市人形製造老舗の娘山田タマと結婚し、その後独立して「丸山娯楽園」を大正11年に創業い...
-
No.28
八木澤 正 -竹工芸-
那須地域は昔から篠の名産地として有名でした。しかし、今は生活様式が変わり、昔のものをつくっても売れない...
-
No.27
藤田 眞一 -小砂焼-
小砂焼は、天保元年(1830年)水戸藩主徳川斉昭の殖産興業政策により小砂に陶土が発見され、水戸に設けられた...
-
No.26
福田 長弘 -烏山和紙-
私は父の紹介で入会させていただき、まだ日も浅い会員ですが、本会が先輩方の築いてこられた歴史のある会であ...
-
No.25
福井 規悦 -印染-
印染とは法被、手拭、のれん、旗、のぼり、などに家紋又はユーザーの名前やロゴを入れて染色する業種であり、着...
-
No.24
日下田 正 -草木染-
名月の 花かと見えて 綿畠 芭蕉。江戸から明治にかけて寒冷地を除いた日本の農村で仲秋から晩秋に見られ...
-
No.23
長谷川 和子 -野州てんまり-
むかし近所の方と母がてんまりを作っていました。私も年をとったら作りたいなと思っておりました。平成9年5月宇...
-
No.22
萩原 幹雄 -樽-
約八十年前に祖父が現在の栃木市で樽屋を開業いたしました。栃木市には大手の味噌屋さんや漬物屋さんがあり、樽...
-
No.21
田中 昭二 -べっこう細工-
昔の親父は良く働いたものです。朝早くから夜遅くまで、朝はめし前に一仕事昼間は普通に働いて、夜は夕食後10時...
-
No.20
田中 梅雄 -和提灯-
私で4代目ですが商売としては3代目で、約100年以上続いています。昔はお寺で提灯を作っていましたが、初代が文字...
-
No.19
田代 芳郎 -早乙女焼-
栃木博覧会開催の1年ほど前、時の旧氏家町長さんより、「来年、開催される栃木博覧会に、各市町村の特産コーナー...
-
No.18
関根 良一 -刃物-
私が伝統ある「下野手仕事会」に入会させていただき、たくさんの方々とお知り合いになることができ、多くの学び...
-
No.17
鈴木 正雪 -木工ロクロ-
木工ろくろ所謂木地師の道に就いて半世紀、祖父が昭和の初期に開業して以来、父に続き、ごく自然にこの職業を歩...
-
No.16
渋井 収 -箕-
私が作る箕は通称、藤箕と呼ばれるもので主な材料は篠竹、藤つる、ヨツドミ、桜の皮などです。それらの材料は雑...
-
No.15
倭文 雄一 -日光指物-
父は銘木業で床柱などを販売していましたが、私は小さい頃より、ものづくりが大好きで、特にその中でも指物に魅...
-
No.14
栗田 英典 -表具-
人生は、どこでどうなるかわからない。手先が器用でもない私が、表具師になりました。公務員の家庭でのんびりと...
-
No.13
川原井 與一郎 -つが野焼-
大地――。いつでも、ここにある大地。思えばなんと不思議な存在だろう。大地は、幾千億の時の中で、植物を育て...
-
No.12
小川 亨 -江戸神輿-
今年(平成25年)で私は52才です。今の仕事(家業の江戸神輿造り)に従事するようになり27年になりました。この...
-
No.11
小川 昌信 -ふくべ細工-
ふくべ細工とは夕顔の実を乾燥させたもの、夕顔の実をむいて干したものが干瓢でこれは栃木の特産品です。父親の...
-
No.10
小川 政次 -神輿-
昭和20年、大東亜戦争(太平洋戦争)の終戦の秋に、16歳で「親方」父、新三郎の元で、木工の仕事の修行を始めま...
-
No.9
大畑 耕雲 -武者絵-
元禄年間より江戸紺屋の商号で染物業を創業・赤穂浪士の討ち入り装束を当家で染めたと伝えられています。紺屋時...
-
No.8
大塚 敏 -桐箪笥-
桐箪笥は昔、女の子が生まれると庭に桐の苗を植えてお嫁入りするときに桐を伐採し、その材料で桐箪笥を作り婚礼...
-
No.7
大塚 明 -民窯(はにわ)-
昭和41年ごろから父のあとを継いで埴輪をつくり始めました。益子の粘土の中でも鉄分を多く含んだ粘土を使い、埴...
-
No.6
大久保 安久 -石佛-
石佛は印度で生まれて、中国、朝鮮を渡り、佛教と共に日本にやって来ました。初めは、一部特別階級の人々による...
-
No.5
大久保 雅道 -結城紬染色-
昔は小山市から茨城県結城市一帯が結城地方でした。国の重要無形文化財で、ユネスコ無形文化遺産に登録された結...
-
No.4
卯野 サチ子 -マクラメ編-
マクラメとは繊維素材を使ったさまざまな作品の中でも機会や器具を使わず、手だけで縦糸を糸どうし交差させて結...
-
No.3
阿久津 華重 -押絵-
30数年以上も前に東京新宿のデパートで「大谷光栄押絵展」を見学して、初めて知る絹布の染描きの押絵作品の美し...
-
No.2
赤池 民子 -野州てんまり-
振り返ってみますと、平成10年の秋、「野州てんまり」の中山先生が、宇都宮市内の福田屋デパートで実演をされて...
-
No.1
青山 万里 -陶芸-
陶芸への道を志して脱サラ、今年で34年。この道を選んでよかったのではないかと思える今日この頃です。まだまだ...