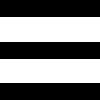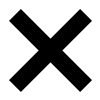作家立松和平(本命 横松和夫 2010年2月8日没)らが制作したドキュメンタリー映画『鉱毒悲歌』のヒカリ座上映(2月28日~3月13日終了/宇都宮市内映画館)の初日に、立松の長男で作家の横松心平氏がトークショーに出演するためにやってきた。在住の北海道からかけつけた横松氏とJR宇都宮駅から車で会場へ向かった。そのタイトなスケジュールの合間にさまざまな話を伺うことができた。
駅から会場までの移動中に、横松氏は「実は僕は宇都宮で育ちましたが、東京生まれなんです。生まれて数か月で宇都宮に来ましたので、故郷といえばやはり宇都宮ですが」と話してくれた。
思いあたった。それは、『1972年、立松和平は妊娠した妻を実家(東京)に帰し、数カ月のインド旅行に出かけてしまった』というような、有名なエピソードを裏付ける横松氏のことばであった。横松氏の生命の誕生は、父の放浪の旅と相まって最初からこのようなエピソード付きであった。

作家 横松心平

赤ん坊の横松氏を抱く立松和平

ドキュメンタリー映画『鉱毒悲歌』
家族は普通に朝ごはんを食べて暮らしていた
「宇都宮の街は大きく変わっていますけれども、やはりここに降り立ったときの懐かしさ、帰ってきたなというような、ふるさと感みたいな落ち着きを感じます。たぶん僕の体の底の部分が宇都宮の水や空気でできているせいだと思うんです」
少年時代に思いを馳せて語ってくれた横松氏は小学校5年生まで宇都宮市で育った。立松和平の長男として生まれた彼の写真は某誌に連載中だったエッセイに掲載されて残っている。そこにはインドから帰ってきたばかりであたかも『途方にくれて』いるようなヒゲづらの父の懐で無心に眠る赤ん坊の彼がいた。
「当時のことはよく覚えていますけれども、基本的にはただの父親なので、振り返ってみても、そのときの父の仕事と我が家の暮らしとは何の関係もなくて、普通の暮らしがそこにありました。ただ、何となくよその家とは違うなというのは小学生なりに思っていました。父は家にずーといて、遅くなってのそのそと起き出して来るんですよ。家族は普通に朝ごはんを食べて暮らしていたんですが、その後書斎にこもって仕事をしていました。時にはずっと家にいない時もありましたね」
物心ついたときの父の記憶は作家という稼業の父の後ろ姿であった。宇都宮に移り住んでからの数年間は家族の生活のためにも市の職員として働いていた。
「父の市役所時代にはあまり記憶がないですね。父がその当時のことを書いたエッセイがあるので、記憶とごちゃまぜになっているような気もしますが、市役所時代の父のエピソードのひとつ、自転車で市役所から帰ってくるときに、途中で飲んできて自転車ごと川に落ちてしまった、半分水に浸かって、月見草が綺麗だった、というようなエッセイがあるんです。僕はなんとなく血だらけ泥だらけになった父が、帰ってきたというような記憶がありますね」
宇都宮市在住時代に立松は『遠雷』で野間文学新人賞を受賞。作品も映画化されて一躍時の人となった。やがてテレビ出演なども含めて「宇都宮から通う時間もままならず」家族で東京へ。横松氏は記憶にはない生まれた場所へと移り住んだのだ。
立松和平のもう一つの有名なエッセイからのエピソード『オニオンスライス』がある。「オニオンスライスの話はしていましたね、書くだけじゃなくて」。眼鏡の奥の優しく笑う瞳は、父立松和平のひとなつっこい瞳を彷彿させる。

ドキュメンタリー映画『鉱毒悲歌』を上映したヒカリ座のトークショーで(右)

トークショー会場
「振り返れば父がいる」
立松和平が『遠雷』で野間文芸新人賞を受賞したときの家族の生活はどうだったのであろうか。「地方」といわれてきた宇都宮の農村を舞台に描いた文学作品に地元宇都宮では色めきたっていた。
「家ではいつもと変わらないですから、騒々しさなどは全くなかったですね、家に持ち込まれてなかったのかもしれないですが、そういうのはなかったですね。父はいろんな活動をして騒然としていたのですが、母(劇作家小山内薫の孫)の家庭も書きものをする人が周囲にいたので、母は慣れていたのだと思います。騒然とした中で暮らしを保つことができる人ですね。後々、大人になってから『遠雷』の映画をちゃんと観たときに、こんなにも身近な場所が映っていたのかと驚きました。ほとんど『遠雷』が書かれたモデルとなった場所がそのまま撮影されていました。それがおもしろいなと思いました」
曾祖父小山内薫、祖父小山内徹(翻訳家)、そして父立松和平と、文筆業としてのDNAを受け継いでいる横松氏であるが「好むと好まざるに関わらず背負っているものが必ずあります。何かを書くということは肉体に根ざしていることなので、どうしても離れられないところがあります。自分のルーツや土地に意識的にならずとも関わっていくことになると思う」と話す。
立松和平が亡くなる年に「立松和平全小説」(勉誠出版)の発刊が始まっていた。各巻に自伝的エッセイを執筆中であった。
「父のエッセイは全集の30巻に掲載する予定で、30冊分の連載が終わったら一冊の本になるという構想だったんです。父がまとまって自伝的なことを書いたことはありませんでしたね。第9巻までの原稿はもう書いてあったんですがその後がなかった。各巻にエッセイの続きのスペースがあるんですが、私が父の自伝を書くのは不可能なので『振り返れば私がいる』というタイトルで父が書いていたのを『振り返れば父がいる』というタイトルで私が間借りしつつ、結局31巻までになったので22回分書くことになりました。そんなに父について書くことあるかなと思ったんですが、書いてみるといろいろ思い出すことや改めて考えることがあったりしまして最後までたどり着きました」
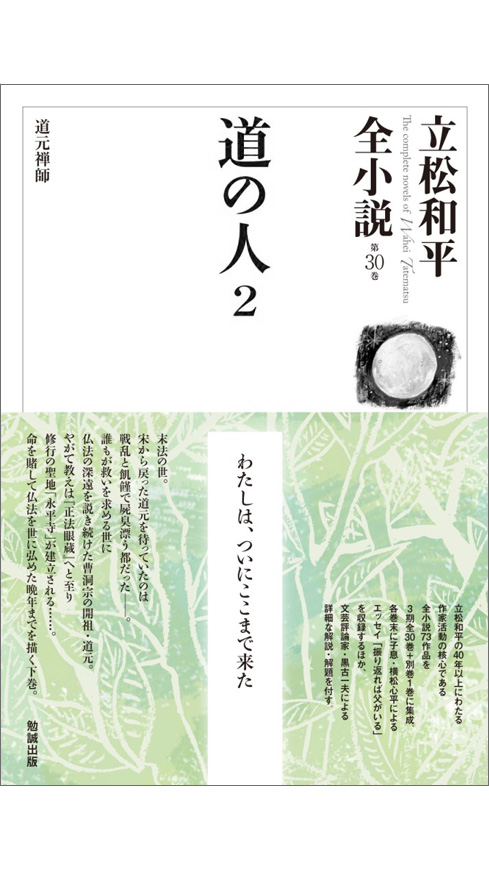
エッセイ「振り返れば父がいる」を収録する『立松和平全小説』(画像は第30巻)
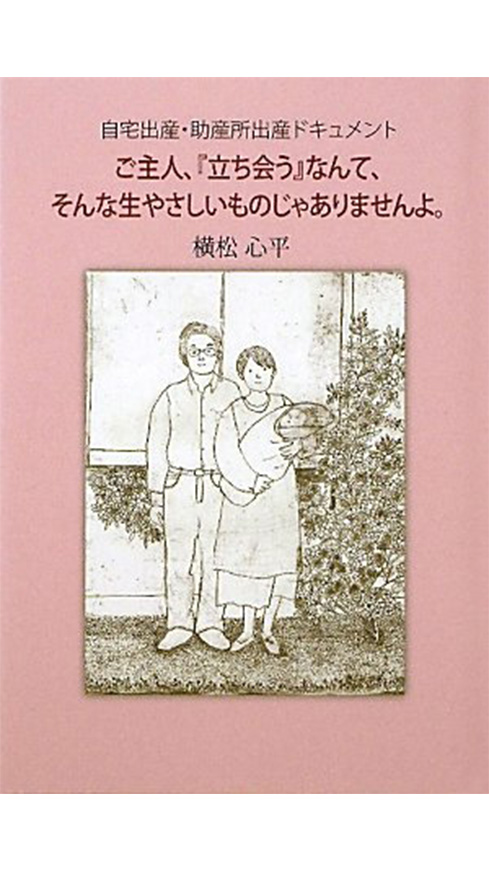
横松心平 著書

横松心平 著書
ドキュメンタリー映画『鉱毒悲歌』
「今思い出すと、『鉱毒悲歌』のロングバージョンのテープが居間にずっと置いてあり、我が家でも気になるものとしてあったんです。父も『これは未完のままで』というような話をしていて存在も僕は知っていたんですが、よもやそれが再び眠っていた虎を起こすように立ち上がり、編集し直しされて映画館で公開されるなど想像もしていなかった。これはすごい事だなと思いました。この映画が恐らく残ってる父の映像で一番若い時のものだと思っています」
横松氏は昨年11月に「足尾に緑を育てる会」に参加した際に上映された映画を見て最後の「立松和平全小説」の30巻目の「振り返れば父がいる21 父への手紙」に以下のように書き記している。
『―――あなた(父立松和平)も映画製作に参加したものの、完成することなくそのままになっていましたね。でも、当時の仲間だった谷博之さんが一念発起し、映画製作委員会を立ち上げ製作を再開させたのだそうです。谷さんらの思いと、あなたが田中正造に再び取り組んでいた思いは、重なる部分があるのではないですか。―――』
そして、この日の映画上映後のトークショーでは次のように話した。
「父はまず『毒―風聞田中正造』(河出書房)という田中正造についての小説を書き、また『恩寵の谷』(新潮社)という足尾銅山についての話を書きました。つまり下流の話と上流の話を書いたんですが、驚くべきことに、しかもそれを同時期に連載していたんですね。特に『毒』は賞を頂いたりして一定の評価を得たわけですが、晩年、亡くなる直前まで書きかけていた小説の1つも田中正造についての『白い河』という小説だったんです。調べてみるとまったく同じテーマについて2回書いた小説は恐らくないですね。ところが田中正造についてだけは2回目をすでに書き始めていた。どうして田中正造についてこだわっていたんだろうというのは、恐らく先祖が足尾にいた(銅山会社側の坑夫派遣の仕事)ということだと思っています」。つまり足尾はまさに横松氏のルーツであったのだ。
世界に通じる扉
横松氏は昨年中国に行ったときに日本の作品を翻訳している人物に会った。『毒―風聞田中正造』(河出書房)を中国語に翻訳して刊行したいと言われたという。
「どうしてですか?と聞きましたら、『足尾で銅山操業の近代化に際して起こった鉱毒事件は中国でも同じように公害を引き起こしている事態と重なって見える』と、だから今中国で読まれるべき内容なんだとおっしゃっていました」
足尾の公害問題はもちろん一地域の問題にとどまることではない。併せて立松和平は足尾をはじめ故郷栃木県を舞台にした小説を数多く書いていることから、横松氏はひとつの答えを出している。
「言うなれば日本のある一隅の地域の事を書いているんですが、それがどこまで成功しているのかは私には評価できないけれども、それが本当に優れた文学作品となったとしたら一気に普遍性を獲得するわけですね。またそれだけでなく、『遠雷』もそうですが私が小学生の時に住んでいた場所、宇都宮の郊外のどこにでもあるような、何でもないような場所ですが、実はそこに都市と農村をめぐる境界の問題があるということを、父が発見して書いたんだと思うんです。ごく地域的なことを書いているのだけれど、それが成功して普遍性を持つと、世界中の人のものになるというのがおもしろいと思っています。
フォークナー(ノーベル文学賞作家ウイリアム・フォークナー/1897―1962年)などは、アメリカの南部の1つの町の話だけしか書いていないのに、今私たちが読んでも感銘を受ける。それが父にとっては「栃木県」だったんだと思います。栃木の持っている意味がうまくすると世界に通じる扉になるというのがすごく興味深いところで、父にとっては栃木という名が自分の書いてるものを伝えていく1つの場だったのではないか、そういう意味で父にとっての栃木は特別な、まあ聖地のようなものだったんじゃないかと思っています」
世の中は生きていくに値する
ものを書いて生きることへの応答とでもいおうか、小説家としてのこれからの展望を伺った。それは最も身近な家族への眼差しから発していた。6人の子どもたちの父親としての眼差しであった。
「僕は子どもがたくさんいるということも大きく影響していますね。子どもに向けて書いていきたいという気持ちが強いですね。今、子どもたちの置かれている状況がかなり厳しいものだというふうに認識していますが、やはり大人の社会が、とても子どもたちに希望を持たせることができる社会になっていないと思います。子どもを持つ親としては未来がすばらしいということを言えないというのは辛いことですよね。しかし、この時代に子どもを持つということは子どもたちに、未来はすばらしいから一生懸命生きていこうよということを伝えなければいけないし、それはただの口約束ではなくて本当に伝えていけるような道筋を作っていかなければいけないと僕は切に思っています。そういう子どもたちに向けて、世の中は生きていくに値するすばらしいものなんだよと、子どもたちを楽しませながら伝えて生きたいという思いが強くあります」
父立松和平も絵本や児童文学などをたくさん手がけていた。それは自分の子どもの幼児期、少年期には子どもに向けて書く余裕がなかったからだという。「自分の子どもには書けなかった分、これからは書いていこうという思いがある」という父のことばが横松氏の胸に残されている。
「僕はそれを踏まえつつ、自分の子どもに向けても伝えて行きたいなと思っています」

作家 横松心平、ヒカリ座ロビーにて