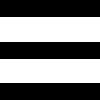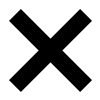自身のスタイル「詩姿」、後進の指導…60年超の多彩な活動
26歳のときに最初の詩集を出版してから60年を超え、今なお第一線で活躍している詩人・山本十四尾(やまもと・としお)さん。詩作への情熱は衰えず、2023年には新しい詩集の発刊を目指している。これまでに18冊を数えた自身の詩集だけでなく、アンソロジーの編集、後進の指導、全国の仲間との交流と現代詩発展のため幅広く活動し、「詩人は肩書ではない。活動と作品で勝負しなければならない」と強調する。生涯現役で詩作を続ける山本さんに活動の軌跡や現代詩への思いを聞いた。

少年時代の戦争体験も リアリズムを追求
2022年11月下旬、山本さんは宇都宮市中央生涯学習センターで開かれた詩人・石下典子(いしおろし・のりこ)さんによる「しもつけ文芸現代詩講座」に講師として招かれた。詩作への取り組み方を説き、受講者の詩には、石下さんとともに具体的な改善点を指摘し、アドバイスを送った。
「1行空けて、舞台の暗転のような効果を」
「反対語を入れることで言葉が際立つ」
そして、「詩は感動と言葉を対生させて生まれる。感動に見合う言葉を使わないといけない。言葉が貧弱では感動が伝わらない。感動が小さくて言葉だけを大げさにしても詩にはならない」と断言。辞書のほかにも類語辞典や反対用語辞典、漢和辞典、ことわざ辞典などを手元に置いて日本語の美しさを勉強するよう説いた。
言葉を磨いて、余分な言葉を削ぎ落とす。
「こういう努力をしないと、詩は良くならない。もっといい言葉があるはず。選び抜いた言葉を使う。この作業をすると、詩は長くならない」
饒舌さを嫌うストイックな姿勢をのぞかせた。
この日、山本さんはいくつかの自身の詩を紹介した。「乳」と題した作品は、目に入ったごみがとれないとき、母親が乳房を出して「薬だよ」と母乳を目に注ぎ込んだ場面をわずか6行で再現し、その感動を「乳はいちばん優しい薬」と簡潔に表現した。太平洋戦争が始まり、6歳で栃木県小山市の親戚宅に疎開。母親に会うのが1年に1回ほどだった少年時代の体験だ。
ほかにも戦時中の体験を語った。疎開先の親戚宅には大きな大谷石の蔵があり、軍隊から2種類の布袋の保管を依頼されたことがあった。トラックいっぱいの袋を石蔵に積み替え、サーベルを提げた軍人は「これは触っちゃいけない」と言う。少年だった山本さんは好奇心から穴を開けた。砂糖と金平糖だった。
「戦争中、草を食べているときに何で軍隊はこんな贅沢品を持っていたのかと思いました」。それから終戦となった。穴を開けたことがばれ、疎開先の家主に「この手が悪い」と、右手の掌に釘を打ちつけられた。血が飛び散り、近くの高台に上ってワラで血をぬぐい、野仏の口に掌を押し当てた。鮮烈な思い出は現代に続く。母親を亡くした後、見に行くと、野仏の顔はすっかり摩滅して目も口も分からなかった。
「終戦の日、8月15日になると思い出す」
掌を見つめる山本さん。傷痕はほくろのような黒い点として残っている。約80年前の記憶と今の野仏の姿は新たな詩に凝縮されているという。体験を基にしたリアリズムが詩を生み出す。一貫した詩作の姿勢だ。

文芸講座の受講者の前に座る山本さんと石下さん

右手の掌を示す山本さん
花の詩人「生き方に仮託し、裏も見つめる」
『雷道』(書肆青樹社、1999年)では、詩集の最高賞・第17回現代詩人賞を受賞。やはりリアリズムが評価された。「乳」もこの詩集で発表した。戦時中の体験をはじめ激動の半生を見つめた詩集だった。
東京大空襲のとき、疎開先から100キロ先の炎を見た。そのとき、父は愛人と火の海を逃げていた。戦争から50年以上経ち、父を介護することになり、その愛人の子である異母妹たちに状況を知らせても返事さえない現実も詩につづった。
「そのような詩を書いても母も兄弟も歓迎しないし、誰も恥部は出したくない。だけど、影の部分を詩にすることで『これは自分と同じ境遇だ』と共感を呼ぶ。共感を呼ばないと詩は成立しない」
そのリアリズムは苛烈さ、厳しさだけではなく、人間への愛や日本人の感性への思いも編み込まれている。
横浜詩人会賞受賞の『葬花』(勁草書房、1986年)では30種以上の花をモチーフにした。26歳の第1詩集『声』から77歳の第15詩集『謝して遺言』の作品をテーマ別に選別し編み直した全集『相*抄と鈔』(歩行社、2019年)にも205編の中に花の詩を60編収めた。だが、山本さんは「花は美しいというだけの詩は一編もない」という。
「ヒイラギの葉のトゲはネズミさえ刺し殺し、ヒイラギの葉を飾るとネズミも通らないが、年数が経つとトゲがなくなり、葉は丸くなる。自分はどうなのか。そこに仮託をする」
「柳の葉は、表面は緑だが、裏は白。人間も裏の部分がある。裏の部分を書いてこそ人間性が見える」
独特の視点で花や葉を見つめ、その特性を書く。そこに人の生き方を重ね合わせる。これまで詩に取り上げた花は300種以上。珍しい花にも目を向けてきた。そして花とともに肉親、人間を見つめてきたのが「花の詩」なのだ。
例えば、『謝して遺言』(歩行社、2012年)には、「逆さ枝垂桜の花が見たい」という高齢の母親の姿が描かれた作品「逆さ枝垂桜」がある。枝先がくるりと上を向く枝垂桜があり、これはなかなか見つけることができない。母親の言葉は作品の中のフィクションだが、詩に託された母親の願望や看病する山本さんの姿、心情はやはりリアリズムに基づくものだ。
花の詩を集めた『アンソロジー花音』(歩行社、2013~2017年)も同様だ。全国の詩人に声をかけて編集した詩集は3巻で641人が作品を寄せ、528種の花が登場。サクラ、キク、バラ、ツバキ、コスモス、ユリ、ウメ、ボタンなど多いが、一般に知られていない花々もあり、1種1編の花の詩は101編。参加者も幅広く、名の知られた詩人だけでなく、小学生の詩もある。多くの詩人がそれぞれの生き方を花に託した。仲間との交流、現代詩の裾野を広げる活動の一環でもある。
アンソロジーでは戦争に関する詩集の編集にも参加した。『原爆詩一八一人集』(コールサック社、2007年)、『大空襲三一〇人詩集』(同、2009年)、『鎮魂詩(レクイエム)四〇四人集』(同、2010年)で、故人から現役詩人の名詩のほか、戦後世代からも作品を公募した。
活動は実に多彩。「詩人は肩書ではなく、作品と活動で評価されるべきだ」というポリシーを貫いてきた。中でも力を入れてきたのが後進の育成だ。

花話会100回記念講演

古河文学館の展示
後進育成に尽力、ボランティアで勉強会
山本さんは20代で詩作を始め、個人詩誌『墓地』を発行した。第1作のテーマは東京の下宿の裏にあった墓地だった。『墓地』はその後、同人誌となり、60年かけて2020年の100号まで続いた。途中から烏山和紙を使った装丁とし、その贅沢さもさることながら、60年100号に及ぶ長期の詩誌も極めて異例だ。
2006年には、おしゃれな詩人に贈られる第2回モデラート賞を受賞した。人の心を打つ作品を書き、生き方がおしゃれ――などの条件に当てはまる詩人が選考対象になるが、新人や地方の詩人を大切にしている点も評価された。
地元の茨城県古河市では「1ページの絵本」で選考委員を務めてきた。古河出身の鷹見久太郎が創刊した絵雑誌『コドモノクニ』、後継誌『コドモノテンチ』の原画や資料を同市立の古河文学館が所蔵、展示しているが、毎年この中からテーマの絵を決めて、オリジナルの詩や物語を募集する取り組みだ。山本さんは第1回から選考委員を続け、15年になった。応募作品も増え続け、毎年、小中学生の部と一般の部(高校生以上)合わせて7000点以上の応募があった。
その古河文学館は山本さんの作品などを常設展示している。2019年10月~2020年2月にはスポット展示で「花の詩人」として紹介。自筆原稿なども公開された。同館は大正ロマンを感じさせる木組みの洋館で、英国製蓄音機EMGマークXb(テンビー)がSPレコードを奏でるサロン、薪を燃やす暖炉が暖かい談話コーナーがあり、展示室とはまた違った、くつろいだ雰囲気がある。
山本さんがボランティアで20年以上続けている詩の勉強会「花話会」は、このサロンの奥にある講座室で開かれている。コロナ禍で中断された時期はあるが、通算138回開催。花に関する詩を鑑賞し、ゲストの詩人も全国から手弁当で駆け付けている。
「現代詩人賞の賞金50万円をどう使うかと考えたとき、詩の活動に還元した方がいいと思った。これから詩を書く人のために使いたいと」
2001年4月から栃木県宇都宮市、小山市、黒磯市(現那須塩原市)、西那須野町(同)、国分寺町(現下野市)などで開いてきた「詩の教室」が「佳話会」、「花話会」と名称変更し、開催場所も古河文学館に落ち着いた。新幹線を使って遠方から来る参加者もいる。
また、「花話会」の活動からは『アンソロジー花音』や『詩姿の原点』が生まれている。
「詩姿」は山本さんの造語。詩人たちの詩への思考と志向と嗜好、詩想と思想を総括して「詩姿」と名付けた。そして、有名無名に関係なく詩人たちの詩作に臨む思いの神髄を文章にしてもらい、勉強会で披露し、後進の育成に役立ててきたのが『詩姿の原点』。2004年の第1集から順次発行を続け、2020年の第1~7集統合最終版では計432人の詩作ノートのエッセンスが収められている。
最新の詩集『心袋』(栃木文化社、2021年)のタイトルも造語。「五感、五欲、五情、五蘊」と章立てし、「喜怒哀楽もいろいろあって、人は20の喜怒哀楽の袋があり、嬉しさ、悲しさなどを心の袋に入れることでストレスを解消できる。だから、心袋を持とう、というのがこのタイトル」と説明する。
また、後進の指導では、下野新聞の「しもつけ文芸」現代詩の選者を20年務めてきたことも大きな功績だ。紙面での批評だけでなく、はがきを送って丁寧に指導してきた。
「20年も続けると、僕の詩姿を真似する投稿者も出てくる。それぞれの感性に従った形があり、みんな違うはず。選者の嗜好に合わせた投稿者が増えるのはよくないので勇退したが、それだけでは無責任なので恥かしくない後任を推薦した」
昨年2021年、石下さんにバトンタッチ。約15年前から指導を受けてきた石下さんは「生涯現役で書き続けることがどんなに難しいことか。ボランティアで勉強会を開き、しかも、誰でもウエルカムで選り好みもしない。詩人という前に人としてどう生きるか、それを教える詩人はほかにはいない。その人間性は作品からもじわじわと染み出してくる。だから、みんながついてくる」と恩師の人となりを説明する。
後を託した山本さんは「現在、女流詩人の中で最も活動しているのが石下さん。欠点は自分を過小評価することだが、僕は全国の会合などに出席するよう言い続けてきた。ようやく全国的な交流が広がり、いま一番注目されている詩人だ」と目を細めた。

花話会編『アンソロジー 花音』
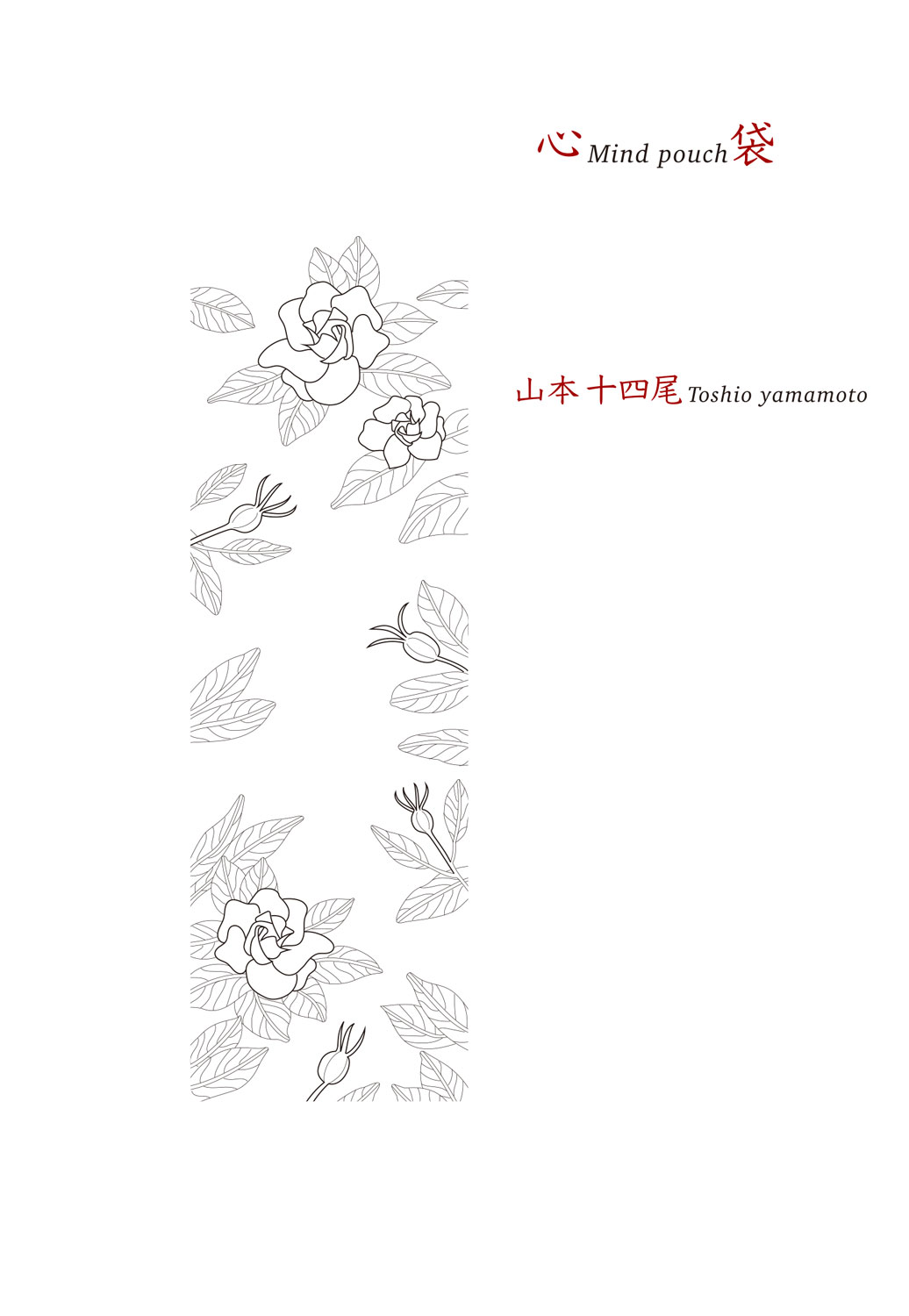
詩集『心袋』