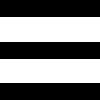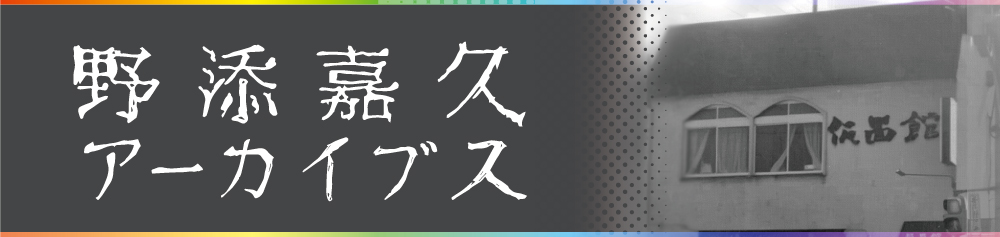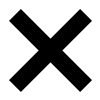序にかえて
足尾(銅山)に関することならばなんでもつかんでみようという私たちの試みを自ら、巨象に挑むアリの姿に似て……と確か、第三期の市民塾〈足尾〉を開くときの呼びかけの文書に書きました。そのことはもちろん今でも間違いであったとは思いません。しかしいささか気取りすぎたかも知れないという思いが生まれてきています。この三年間、多くの市民の方がたとともに学んで来た結果、やっといまわかって来たことなのですが、ほんとうに“足尾“は一筋縄でとらえられるものではないのです。
明治のはじめ、多くのヤマの中で特に足尾銅山の発展と鉱毒被害の拡散とが、近代日本の殖産興業政策の真の姿を最もよく表わしているということは、いまやほとんど常識となっております。しかし私たちはこの両極にある二つのことがら、つまり銅山の発展と鉱毒による悲劇をこれまで余りにも単純に善玉悪玉という図式で示しては来なかったでしょうか。 銅山の操業そのものの停止を農民たちが求めたとき、単に害を被るからというにとどまらず、日本という新興国家の「近代化」政策そのものを告発し、拒否したはずなのです。

長編記録映画「鉱毒悲歌そして今」より。右から二番目が野添嘉久氏
当の農民たちがその点をどれほど自覚していたかはもちろん疑問ですが、以来一世紀を経て多少は歴史から何かを学びとる術を知った私たちがことの本質をとらえ、継承していかなければ、あの筆舌に尽しがたい田中正造と農民たちの辛苦を、真にこの世に生かすことにはならないのではないでしょうか。また同時に、1983年というこのときに私たち自身の周囲におきるさまざまな事象ー原発、成田、軍備増強、右傾化等々に私たちがどう対処していけばいいのか、つまり、私たち自身の根源的な有りようを問うことにもなるわけです。
自分で自分に剣をつきつけるような苦しい作業には違いありませんが、いま私たちが足尾を学ぶことの意義は、まさにここにあると思うのです。
この3年間に学んだことがもう1つあります。それは、あらゆる事象の陰に見え隠れする人間の姿のことです。悲しさというのか面白さというのか、あるいはやりきれなさ、せつなさといえばいいのか、ともかく人間そのものに対する興味と言えるでしょうか。
こういう言い方はある危険性をはらんでおりますが、敢えて誤解を怖れずに言えば、神田川に身を投じた市兵衛夫人の苦悩、戦列を離脱してゆく農民の落ちくぼんだ暗い目、古河の撤退におびえながらも足尾に生きる人々などを、非情な資本の鉄則や政治の論理の貫徹とともに見すえていきませんと、やはり足尾を今後に生かすことにはならないと考えるようになりました。
いまやっと到達したこの私の考えかたに、市民塾〈足尾〉が沿うものであったのかどうか、全く自信はありません。しかし、私たちのたどって来たこのジグザグの道を敢えてそのまま世の人々に提供しようと思います。ささやかなこの試みが何かのお役に立てば望外の喜びです。
1983年6月
野添嘉久
【出典:「なぜ、今、足尾か」1983年6月25日発行より 編集:市民塾〈足尾〉 発行:下野新聞社】

長編記録映画「鉱毒悲歌そして今」より