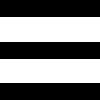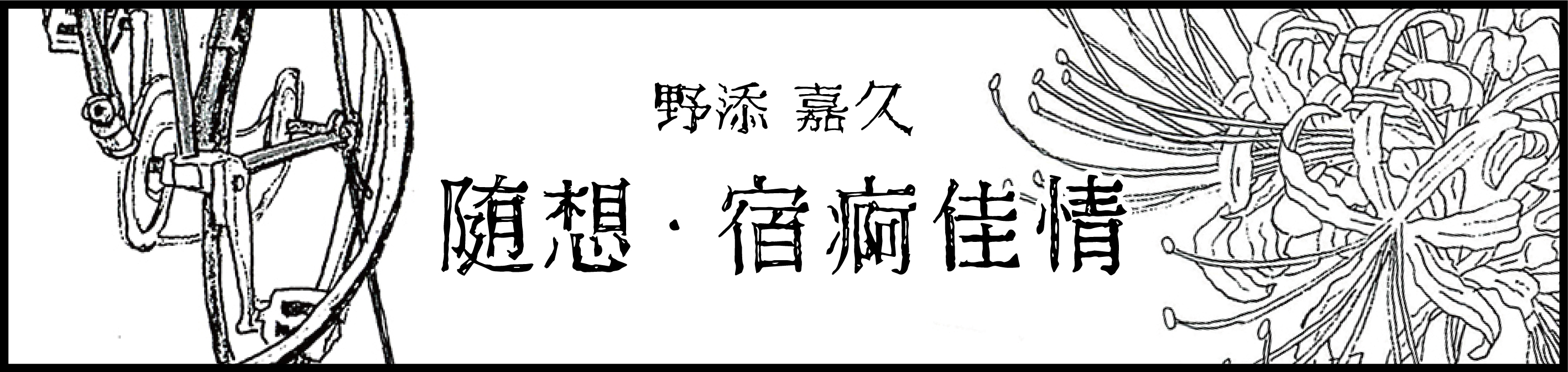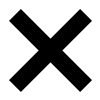『賛沢な旅』 97・3・28
今の私にとっては到底許されない賛沢な旅をして来た。列車、船を乗り継いでまる四日がかりで那覇へ。長女宅に三泊後は飛行機で羽田へと、ゆったり日程の上に妻、次女まで伴にするという、まさに大名旅行だった。
水俣の先達や旧友たちは暖かかったし、各地の海も山も穏やかだった。感傷旅行と笑わば笑え、もう思い残すことは何もない、とは無論ウソウソ。
三島由紀夫のように、作品を書き出す折に、その結句まで既に頭にあるなら問題はない。だが私の場合には、動き出した筆の先がどこへ辿り着くのか見当もつかないし、推敲にもえらく時間がかかる。この点は彼の師の川端康成と一脈あい通じていると、おこがましくもほくそ笑むのだが、それはともかく、そんな私が失明した場合には、どのようにして文章をものしたらいいのか。今その技術的な方法を真剣に模索している。
おそらくは動燃・東海の事故のとばっちりだろう、同じ科技庁の管轄下にある放医研からは入院期日の連絡がない。特に今月に入ってから右の聴力と視力の衰えが激しい。放射線の照射は無論それをさらに加速させるのだが。
『水俣の燻製』 97・4・8
数年前、水俣。
妻が燻製をつくると言いだした。器具一式を取り寄せ、堂々たる陣立てだ。
度重なる試行錯誤の末、黄金色に輝く太刀魚の燻製を、たぶん世界で初めて完成させた。意外に評判がいい。到頭、東京の某消費者グループにまで売り込んだ。
保健所への申請、商工会議所での展示、化粧箱の手配など、趣味の域を越えるにつれ、私の仕事も増えた。眼前が海とはいえ、新鮮で安い材料の仕入れは、案外手がかる。ときには、鹿児島の阿久根魚協まで、早朝の国道3号線を疾走した。
「桜のチップじゃだめ。あの色の秘訣はね、特産の夏蜜柑の枝にあるんだから」
燦然と輝く第二の水俣名物をーー。宇都宮への帰郷を前に、妻はノウハウの伝授を試みた。不首尾に終わった。
顔見知りの商議所の識員が言った。
「私ゃ水俣の出じゃなかばってん言えるのかも知れんですが、ここん人は誰でん、よそから来んなすった人ば、すぐには信用せんとですよ。やっぱり、あん病気がですなァ、あん病気がですたい・・・・・・」
『頑張れオンブズ』 97・4・11
国の内外ともに憂鬱な事件が続く。おそらく人間の本性は、何千年も前から愚かなのだ。だが、主として先進諸国では、暗冥の中世を脱してから今日まで、自らが不完全な存在であることに気づいた人間は、徐々に法律を整え、制度を整備し、また罰則を設けるなどしてその不備を補ってきた。その意味では、人間の作るシステムは、少しずつではあるが進歩してきたと言える。その端的な一例が、まだ完全とは言えないだろうが、義務と責任とに裏打ちされた「情報の公開と共有」である。
わが栃木県、市町村ではどうか。二つのオンブズ組織が誕生したとはいえ、官庁側の「依らしむべし」との態度に阻まれて、市民の知りたい情報はまだまだ闇の中にあると聞く。為政者たちに時代の趨勢を弁える感覚が乏しく、また市民の側にもアリの一穴を穿つ力が足りなかったらこの折角の滔々たる時の流れに乗ることはできない。そして、市民の政治不信は加速されるばかりであろう。二つのオンブズ組織に声援を送りたい。
<4・8 下野新聞>