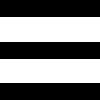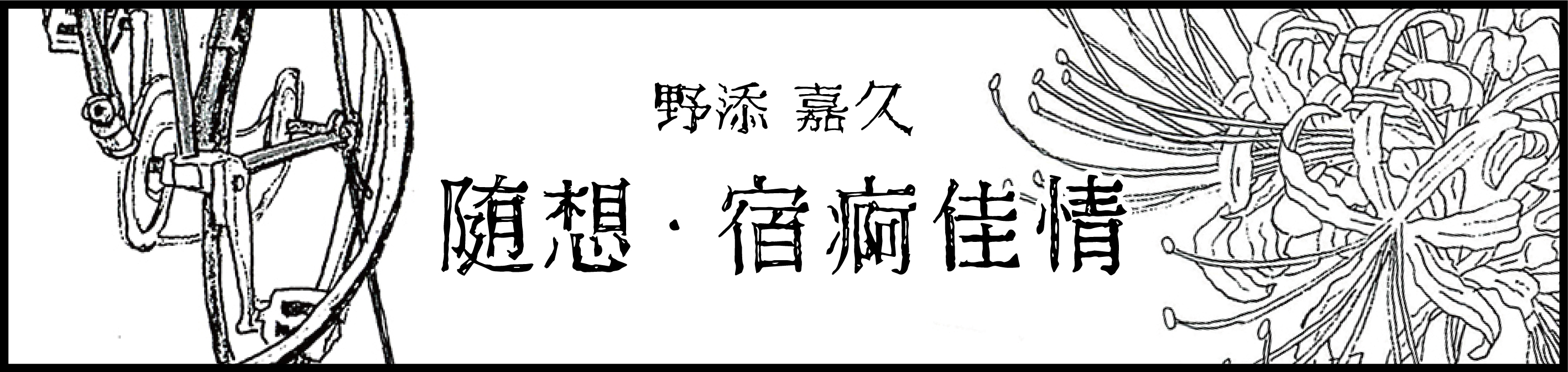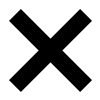『反発から闘病へ』 97・6・11
高校時代の友人Sが、ガンに坤吟していると共通の友から知らせがあった。「奴にはガッツがない。あれじゃジリ貧だ。それに比べて君は・・・」
そうではない。私には、柳田邦男氏の数多の著作に出てくる患者さんたちのような、強烈な『生』と『仕事』への執着に叱咤されつつ病魔と闘って来たわけではない。当初、もし助からぬ定めならば、何よりも心身ともに安楽な死を願ったし、私でなければならぬ程の付託を誰からも受けてはいない。
私の父が死んだとき、年長の従兄弟が「叔父さんには頑張ろうという気持ちがなかった」と言った。父は長年の間胃弱で苦しみその果てに死んだ。52年の短い生涯のうち、健康だったのは半分くらいだったろうか。我が家計は母に支えられ、晩年の父はすでに投げていた。だから従兄弟の言葉は事実ではあったが、私の耳には不快だった。
昨年の春、ガンであることを告知されたおり、私はこのことをすぐに想起した。私に病いに立ち向かう気力があるとすれば、この一言への反発から生まれたものかも知れない。さて、Sをどう激励したらいいのだろう。
『止むを得ぬ暖昧』 97・6・19
以前、ある会社の総務課の末端管理職になったとき、会社構内の消防自動車が車体検査を受けていないことを知って上司に訊いた。600メートル離れた社宅が火事になったときに出動できないと。彼曰く「車検なんて。火さえ消せば褒められるさ」。だが、社宅に隣接する家が、またはその隣の、あるいは更にその隣の家が万が一の場合に、この消防車を出すべきか否か。
わが国周辺に、予想を超えた事態が出来したときにどうするか、で様々な議論がある。たかが社宅の近辺にでさえ、車検なしの車を出すかどうかで、新米係長は心を痛めるのだから、全くスケールの違うこの議論の結論は難しい(はず)。日本人と白人のリーチの差とする説がある。そうかも知れない。
さて、放医研での最後の日、私、が受けた説明は、ほぼ完全に治ったとも取れるし、逆にまだかなりの日数を経なければ何とも言えないとも解釈できる、いわゆるグレー・ゾーンに属するものだった。この暖昧な言葉は、医師としての良心が言わしめたものだろう。だから私は、これから暫くの聞はこの区域をさ迷うことにする。この場合には、いささか暖昧でも止むを得ない。
『縄文社会のレベル』 97・6・22
数年前、スイスの山中で、約5千年前の男が発見された。銅製の斧を持ち、防寒服をつけ、靴は二重で、火種を入れる桶も携えていたそうだ。
この時代に銅製品はなかったというのが今までの定説だし、また、衣服の獣革の綴じ目の巧拙から専門職の存在が窺えるらしい。とすると、この人たちは、技術的にも社会的にも、今までの常識より遥かに豊かな文化を育んでいたと言える。
私たちは、5千年前の縄文人はほとんど半裸に近く、石器と棍棒程度の道具だけで狩猟、採集生活をしていたとの印象を抱いて来た。おそらく子供のころに見た絵の記憶によるものだ。その頃は、今よりもずっと温暖だったという。それでもこの時代の遺跡の80%が中部以北にあることを考えると、彼らは防寒具や調理方法、気密性の高い住居など、私たちの想像よりずっと進んだ技術と社会性を持っていたのではないか。各地で新しい遺跡が発見されるたびに、私たちの常識は訂正を余儀なくされる。彼らは、私たちの倣慢さを笑っているかも知れない。
また、縄文期の人骨には、抗争によると見られる損傷が全くないという。洋の東西で進み方の異なる道具や住居のことよりも、こちらの方が遥かに鋭く現代を照射している。本日、G8が始まり、ポル・ポトが拘束された。

田中正造大学での映画「鉱毒悲歌」上映会と講演会