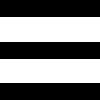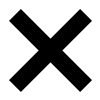長編記録映画『鉱毒悲歌』を語る
いくつかのマス・メディアにも紹介されて華々しく開講の運びとなられたこの田中正造大学の第二講に、私たちの映画『鉱毒悲歌』をとりあげていただき、まことに有難うございました。
物理的に長時間の映画(187分)であるということに加えて、少し特異な編集をしてありますので、最後までご覧になられて、いささかエネルギーを消耗されたことと、深くご同情申し上げます(笑い)。
さて事務局の方から、映画について何か語れということですが、突然のこととてそれらしい用意もございませんし、また、映画としての出来がどうあれ、ともかく1つの作品としてこの世に存在しているからには、それ自体を離れて何かを書いたり、喋ったりすることは、あまり良いことではありません。しかも、この映画の制作について、私は責任者でもありませんし、ナレーションの原稿を執筆したのも他の方です。
しかし、折角のチャンスですので、この映画が十余年前、宇都宮の若者たちの手によっていかにして作られ始めたかをお話ししようと思います。それはおそらく、何らかの意味で皆さん方の今後の参考になるものと考えるからであります。また、田中正造大学の事務局によれば、この私のつたないお話がいつの日にかは活字化されるであろうということですので、「記録」ということに重点を置きながら、思い出を辿ることにいたします。今までにも上映の機会を得る度に、観客の方々には口頭ではその辺の事情をご披露してはきたのですが、文章として残るチャンスは今日が初めてのことであります。

野添嘉久氏

故岩崎正三郎氏の説明を聞く、谷博之氏、立松和平氏たち
発端・・・1973年
この年、あるいはその前年、田中正造の後半生の闘いを描いた映画『襤褸の旗』(吉村公三郎監督、三国連太郎主演)が完成いたしました。このとき、宇都宮市での上映活動を担ったのが、「自主上映の会」という10人ばかりの会員を擁していた団体でした。確か、ここ佐野や藤岡町でもかなりの観客を集めたと聞いておりますし、佐野市教育委員会はそのプリントを購入して持っているはずです。
さて、この当時、この「自主映画の会」と「襤褸の旗・製作上映委員会」の瀬戸要氏(制作担当〉との間で、具体的にどのような話し合いがあったのかについては、私は詳しく知りません。ともかく、この二者を母体として、あるいは「自主上映の会」が主体となって「谷中村強制破壊を考える会」が生まれ、次いでこれが映画『ドキュメント・谷中村』を作ろう、という動きに発展していきます。この渦の中心に位置していたのは、今宇都宮市議をしている谷博之氏、今は作家として活躍している立松和平氏たちでした。
私の想像によれば、『襤褸の旗』が強制破壊の時点で終わっているので、その後の谷中村民の足跡を辿ろうとしたのです。
私はその頃、今風に言えばライブ・スポットを作ろうとしていた矢先でしたので、このグループのメンバーにはなりませんでした。しかし(この正造大学へ参加される方々もそうですが)こんなことを始める人々は、もともと何らかの横の繋がりがあるものです。そんなわけで、正式の会員ではありませんでしたが、彼らの動きの概略は私の耳にも届いておりましたし、現に何度か彼らの会合の席に招かれたこともありました。
さて、こうして勉強会として誕生した「谷中村強制破壊を考える会」が、映画『ドキュメント・谷中村』を製作しようと動き出すまでには、さほどの時間はかからなかったようです。当時の記録の多くは散逸してしまっておりますが、僅かに残されているものから想像しますと、そういうことになります。当初の計画では、60分程度のもので、費用は550万円くらいと踏んでいたようです。もっとも私の記憶では、細かな計算や見積りから出た数字というよりも、500万ぐらいあればできるでぇと瀬戸さんが言うのでそうしたのだと聞いたような気がします。瀬戸さんはそんな感じの人ですので、さもありなんというところでしょう。そうすると、50万円は通信費、食事代などのいわゆる諸雑費に充てる予定であったのかも知れません。
さて、おそらく1973(昭和48)年の春にできた「ドキュメント・谷中村を作る会」は、早くもその年九月には、北海道の栃木部落(正式には常呂郡佐呂間町字栃木)に、演出の中村和夫氏、カメラマンの趙根在氏(日本名は村井欽二)の二名を派遣しています。これは、資金集めのメドがつき、シナリオもある程度練られたからのことではなくて、突如耳に入った栃木部落の秋祭を撮影しようとして、取るものも取り敢えず旅立ったもののようです。なにしろ当時の記録では、半年の間で作ろうとしていたようですから、期日の決まっている祭については充分相談してからなんて、やる暇がなかったんだろうと思います。おそらくシナリオの方がこの撮影行より後にできています。
諸々の準備不足の点は、撮影と平行して解決していけばいいとした(であろう)この熱に浮かされたような状態は、会員の多くが20歳代前半であったということから常に徴笑をもって許されてきましたが、もちろん後になってさまざまな問題を生むことになります。

栃木部落の廃屋(林えいだい氏撮影)