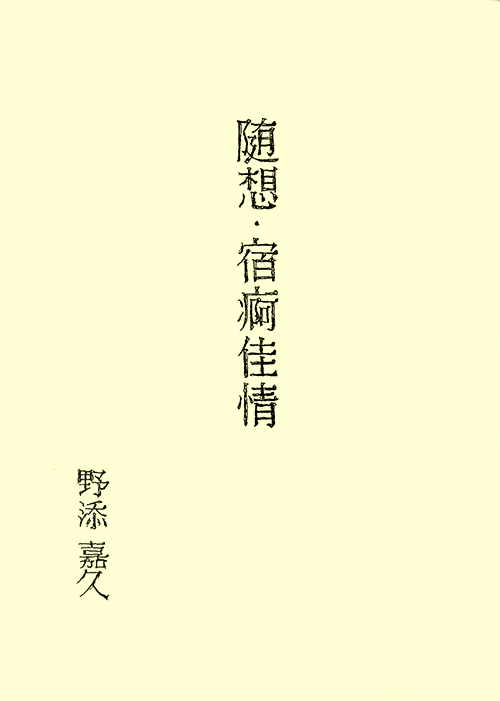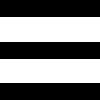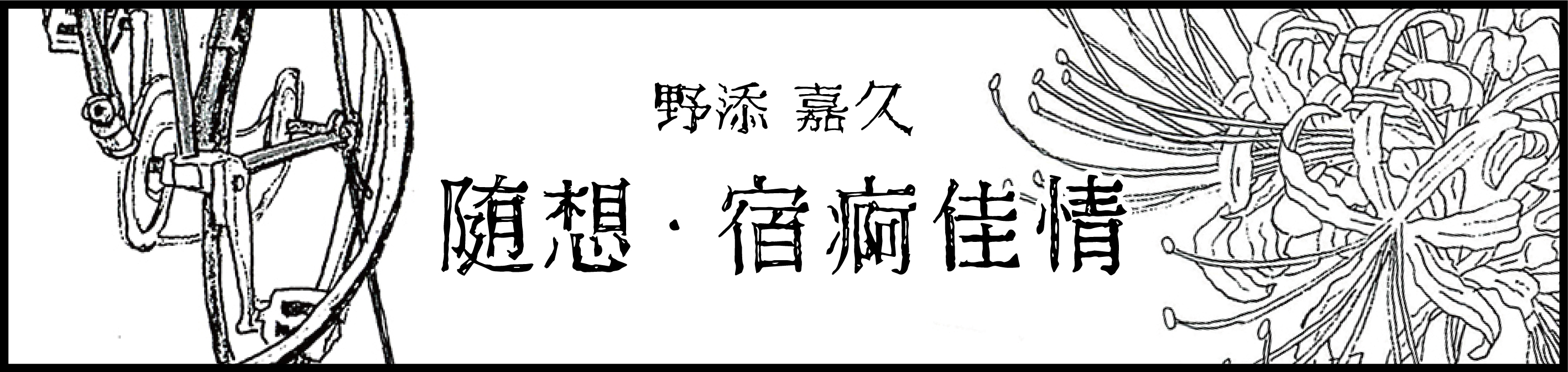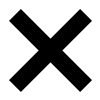随想・宿痾佳情
「随想・宿痾佳情」は野添嘉久氏の個人的な思索や日常生活の観察、そして自身の病気との闘病経験を織り交ぜながら、彼が長年深く関わってきた社会問題や歴史認識について綴ったエッセイです。
1996年11月から1998年1月にかけて執筆されました。
『義父母の席』96・11・24
晩秋の一夕、久方ぶりに妻の実家を訪れた。収穫も終わり、渺々と拡がる田園のそこかしこに散らばる平地林が、今は美しく色づいている。
「少しァ、飲めっぺや。外出できんだかんよ」
80をいくつか越した義父が、晩酌の相手が現れた欣びを満面に浮かべ、やや覚束ない足取りでいつもの場所に陣取って言う。家人はもとより、たまさか請じ入れられた近隣の人々も、決して義父の席を侵すことはない。
「今日はハァ、暖ったかかったなやァ」
夕餉の総菜の一部を抓みとして食卓に並べ終えた義母は、酒の支度を嫁に任せて義父の右隣にそっと座る。
「極楽だなや、今の暮らしァ。もってねぐって、惚けてらんネェ」と義母。
「バァカ。そったらこと言うがら、若ェもんに嫌われんだわ」
義父母の席は、間もなくやって来る新年にも安泰に違いない。
『紅葉と人民』 96・11・28
病院の裏庭の木々の葉が一様に色づき、日毎に初冬の風情を濃くしてゆく。
散歩の折りにたまさか仰ぎ見る紅葉は、木の種類によって決して同じような輝きを呈してはいない。(これは人間の身勝手だが)真に称賛に値する色合いの紅葉は少なくて、逆にちょっと汚らしいなと感じさせるものさえある。それなのに、例えば塩原に一日遊び、淡い陽光に映える山なみを遠く眺めれば、個々の樹木のクセは消え、全山これ一幅の絵画に変ずる。
まだ学生だったころ、唯物弁証法を説いた本の中で、日共系らしい著者がしきりと「人民という言葉が好きだ」と繰り返すのを、どこか信用できないなとうさん臭さを感じたことを思い出す。
頑迷、日和見、無定見、狡猾、下劣などなど・・・これが個々の『人民』なのだが、果たして紅葉と同じように、マスとして遠望すれば、美しく照り輝く存在なのであろうか。
『まぼろしの天草』 96・12・5
小さな蕾をつけた黄水仙の葉を、年老いた伯母は、布切れで一枚一枚丁寧に拭う。生まれ育った茅葺き屋根と山合いの段々畑を瞼に浮かべているのかも知れない。
帰りたいといくら言われでもネ、あの田舎じゃ測量屋としてはやってけないよと、還暦近い従兄がやっと買った八王子の戸建住宅には、申しわけ程度の庭がついているだけだ。だから、黄水仙の株もたかが知れているのだった。
「水仙はね、三重にもいっぱいあってねェ」
曲げていた腰を伸ばしながら、伯母が言う。いつかは訪れるに違いない帰郷の日に備えてか、関西風のアクセントをまだ離さない。
「でも、三重よりうんと寒いの、ここは」
「叔父さんの天草と同じでね、お袋の三重はもうありゃしないんだよ」
後ろで従兄が、庭に向かって言う。
父の生まれは八代から球磨川を遥かに遡った人吉近くの寒村。天草なんてそう何度も眺めたわけでもなかろうに、父はその美しさを母と私に事あるごとに繰り返し、そして31年前の暮、ひっそりと逝った。
当時、父の故郷に納骨を、と提案した私に、従兄はどこまでも現実的だった。
〈道路の拡張で、ご先祖さまの墓地が削られるらしいよ。どうも話は逆だな〉
かくて父は、宇都宮の霊園で、天草を思い続けている。
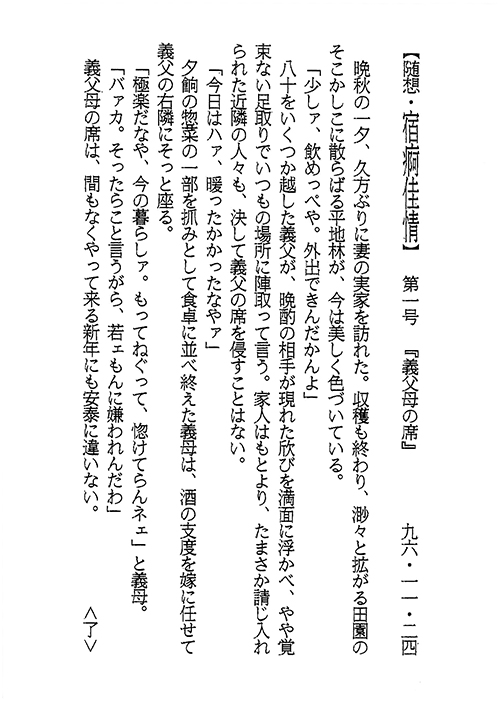
随想・宿痾佳情